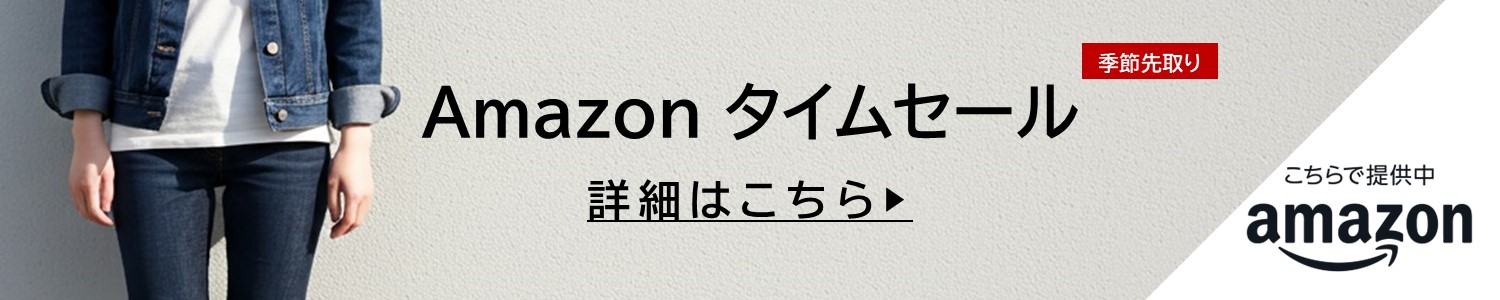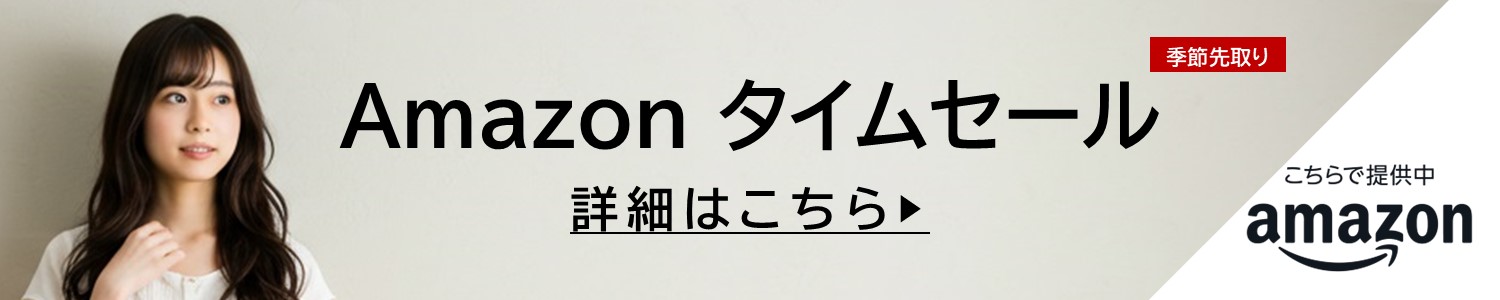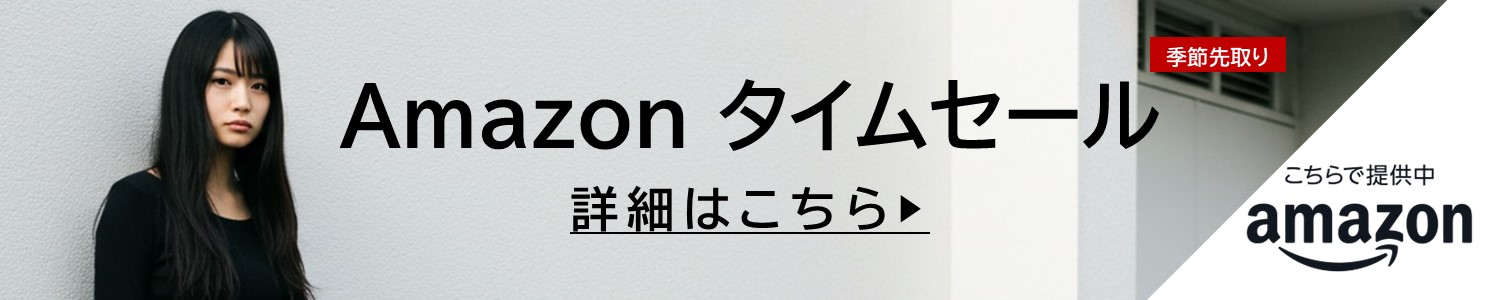「intervention」の意味や使い方をわかりやすく解説します。
意味介入、干渉、仲裁、調停、軍事介入、治療的介入、妨害、口出し
発音記号/ˌɪntɝˈvɛnʃən/
※音声が再生されない場合は読み込みを待つかブラウザ変更をお試しください。
「intervention」の意味と使い方
interventionは「介入、干渉、仲裁」という意味の名詞です。他者の問題や紛争に対して、当事者ではない第三者が積極的に関与し、事態の改善や解決を図る行為を指します。政治、経済、医療など、様々な分野で使用され、状況を変化させる意図的な行動を表します。
「intervention」を使ったフレーズ
「intervention」を使ったフレーズや関連語句を紹介します。
medical intervention(医療介入)
government intervention(政府介入)
military intervention(軍事介入)
early intervention(早期介入)
economic intervention(経済介入)
interventionを使ったよく使われるフレーズは「early intervention(早期介入)」「military intervention(軍事介入)」「market intervention(市場介入)」「crisis intervention(危機介入)」などがあります。
「intervention」の類義語・同義語
interventionの類義語には「interference」「involvement」「mediation」「arbitration」「intercession」などがあります。interferenceは干渉、involvementは関与、mediationは調停、arbitrationは仲裁、intercessionは仲裁やとりなしといった意味合いを持ち、文脈によってinterventionの代替として使用できます。
「intervention」の反対語・対義語
「intervention」の反対語には「non-interference」「laissez-faire」「abstention」などがあります。non-interferenceは不干渉、laissez-faireは自由放任主義、abstentionは棄権や自制を意味し、いずれも介入や干渉を避ける、または積極的に関与しない状態を表します。