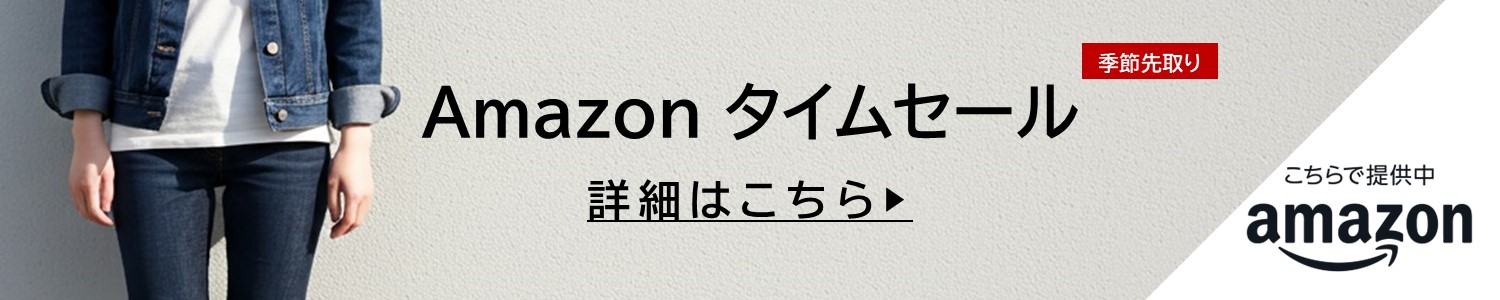「stroke」の意味や使い方をわかりやすく解説します。
stroke
意味脳卒中、一撃、打撃、なでる、ストローク、筆運び、漕ぎ、幸運、打つこと、影響、発作
発音記号/ˈstɹoʊk/
意味脳卒中、一撃、打撃、なでる、ストローク、筆運び、漕ぎ、幸運、打つこと、影響、発作
発音記号/ˈstɹoʊk/
※音声が再生されない場合は読み込みを待つかブラウザ変更をお試しください。
「stroke」の意味と使い方
「stroke」は「脳卒中、一撃、打撃、なでる行為、泳ぎの型」という意味の名詞・動詞です。名詞としては、脳卒中や打撃、泳ぎの型などを指し、動詞としては、なでる、打つといった意味を持ちます。文脈によって意味が大きく変わるため、注意が必要です。
「stroke」を使ったフレーズ
「stroke」を使ったフレーズや関連語句を紹介します。
stroke of luck(幸運のいたずら)
have a stroke(脳卒中になる)
stroke someone’s ego(お世辞を言う)
at a stroke(一挙に)
a stroke of genius(天才的な閃き)
the final stroke(最後の一撃)
have a stroke(脳卒中になる)
stroke someone’s ego(お世辞を言う)
at a stroke(一挙に)
a stroke of genius(天才的な閃き)
the final stroke(最後の一撃)
「stroke」を使ったよく使われるフレーズは「a stroke of luck(幸運)」「in one stroke(一挙に)」「paint strokes(筆致)」などがあります。
「stroke」の類義語・同義語
strokeの類義語には「hit」「blow」「caress」「pat」「rub」「touch」などがあります。hitやblowは打撃、caressやpatは愛撫、rubは摩擦、touchは触れるといった意味合いで、strokeが持つ文脈によって使い分けられます。
「stroke」の反対語・対義語
「stroke」の反対語には「failure」「setback」「decline」などがあります。これらは、脳卒中などの「発作」の意味でのstrokeに対して、機能の低下や喪失、または改善の失敗といった意味合いで用いられます。また、「撫でる」の意味でのstrokeに対しては、「hit」「slap」などが反対語として挙げられます。