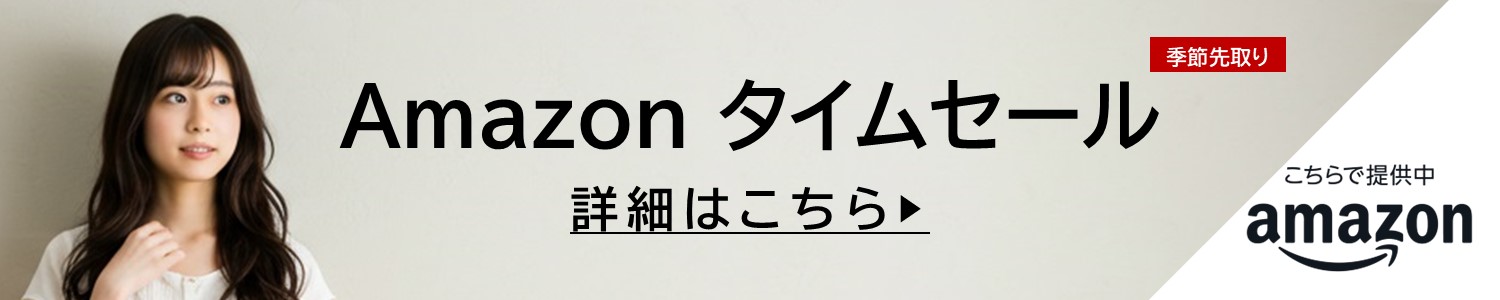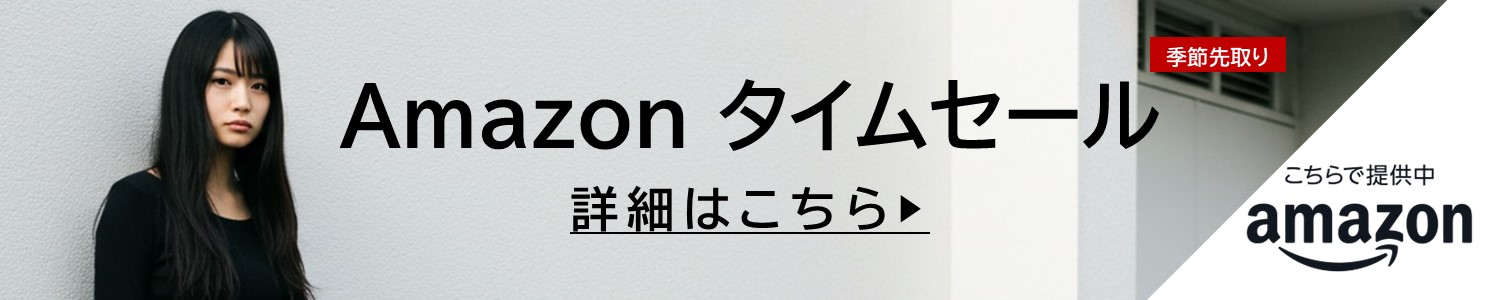「servant」の意味や使い方をわかりやすく解説します。
servant
意味使用人、召使い、奉公人、使用人根性、貢献者、尽力者
発音記号/ˈsɝvənt/
意味使用人、召使い、奉公人、使用人根性、貢献者、尽力者
発音記号/ˈsɝvənt/
※音声が再生されない場合は読み込みを待つかブラウザ変更をお試しください。
「servant」の意味と使い方
「servant」は「使用人、召使い」という意味の名詞です。個人や組織に雇われ、家事や雑用など、様々な仕事を行う人を指します。歴史的には身分の低い人が行う仕事でしたが、現代では専門的なスキルを持つ人も含まれます。
「servant」を使ったフレーズ
「servant」を使ったフレーズや関連語句を紹介します。
servant of God(神の僕)
a faithful servant(忠実な召使い)
domestic servant(家政婦)
servant leadership(サーバント・リーダーシップ)
the servant problem(召使い問題)
servant class(召使い階級)
servant’s quarters(使用人部屋)
a faithful servant(忠実な召使い)
domestic servant(家政婦)
servant leadership(サーバント・リーダーシップ)
the servant problem(召使い問題)
servant class(召使い階級)
servant’s quarters(使用人部屋)
「servant」を使ったよく使われるフレーズは「public servant(公務員)」「faithful servant(忠実な僕)」などがあります。public servantは国民に奉仕する人を指し、faithful servantは主人や組織に忠実な人を意味します。
「servant」の類義語・同義語
servantの類義語には「employee」「worker」「attendant」「helper」「domestic」などがあります。employeeやworkerは雇用関係にある人を指し、attendantは特定の場所や人に付き添う人、helperは手伝いをする人、domesticは家事をする人を意味します。
「servant」の反対語・対義語
「servant」の反対語には「master」「employer」「leader」などがあります。masterは主人、employerは雇用者、leaderは指導者という意味で、いずれもservant(召使い、使用人)とは対照的な、指示や命令を与える立場を表します。